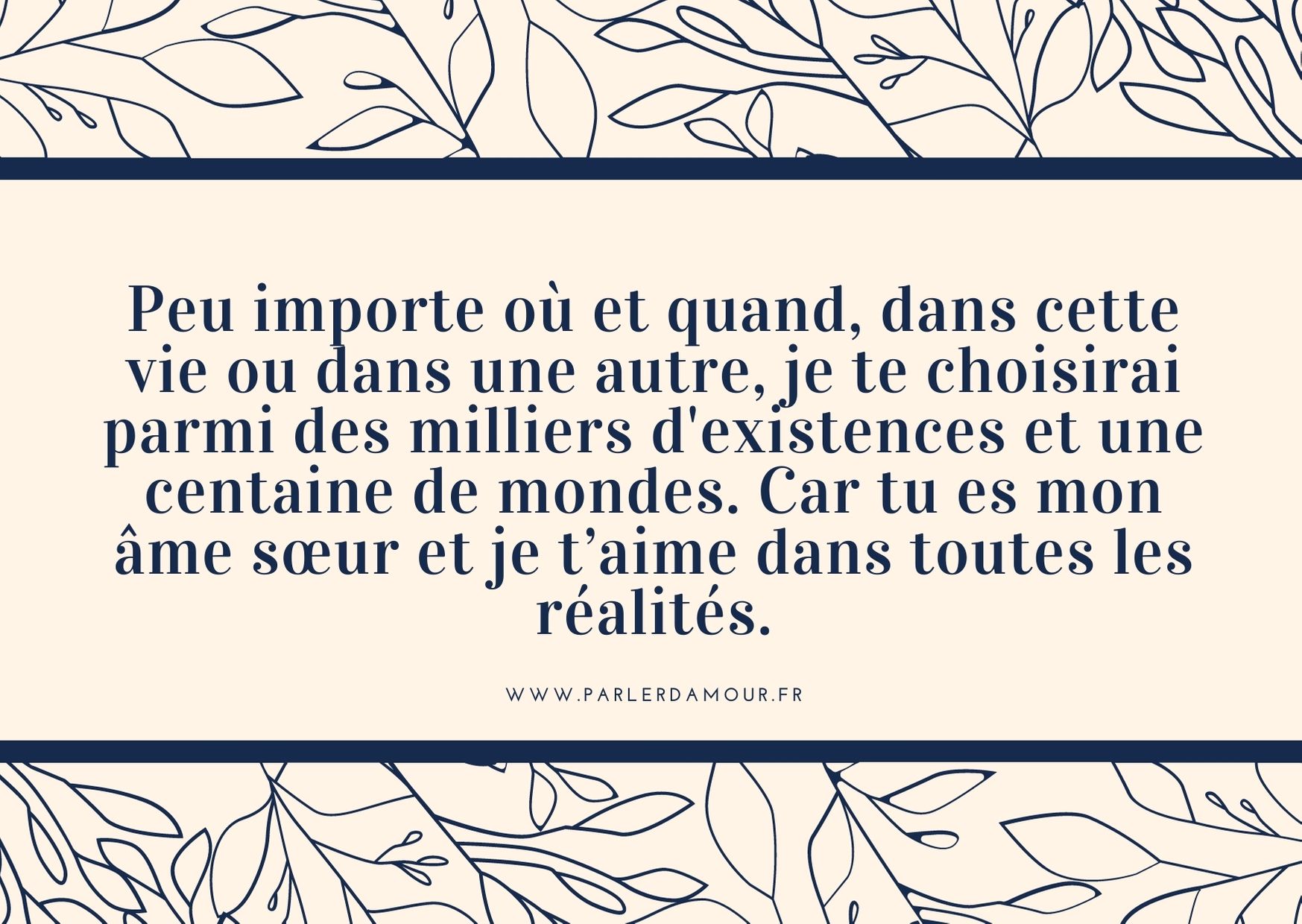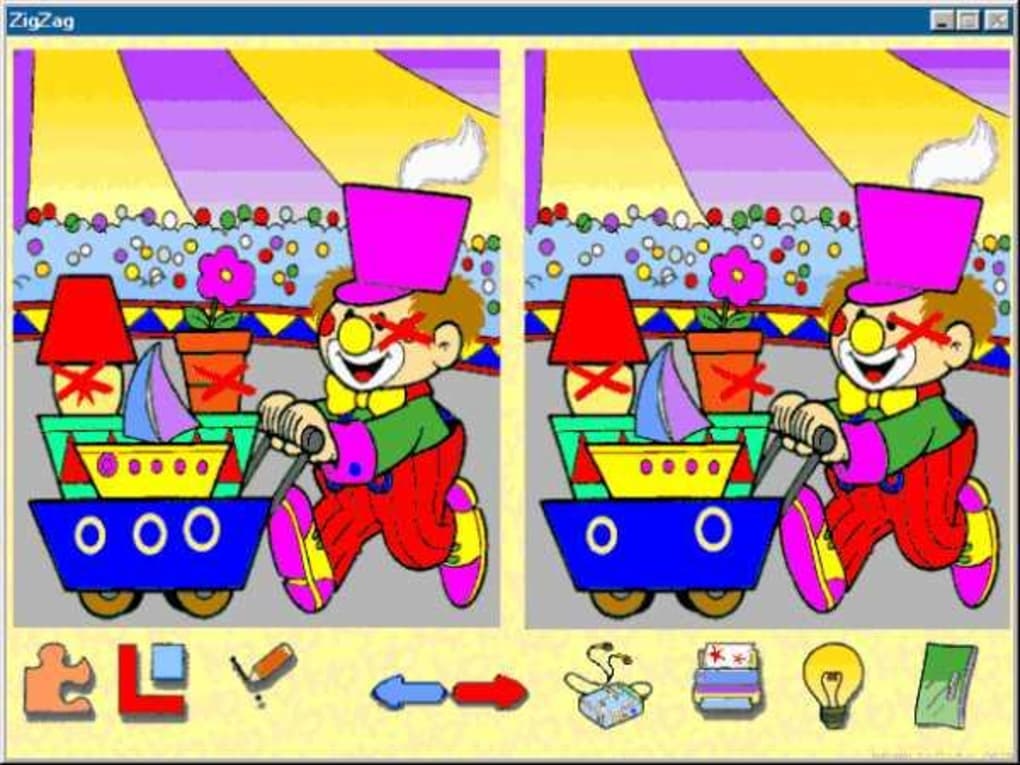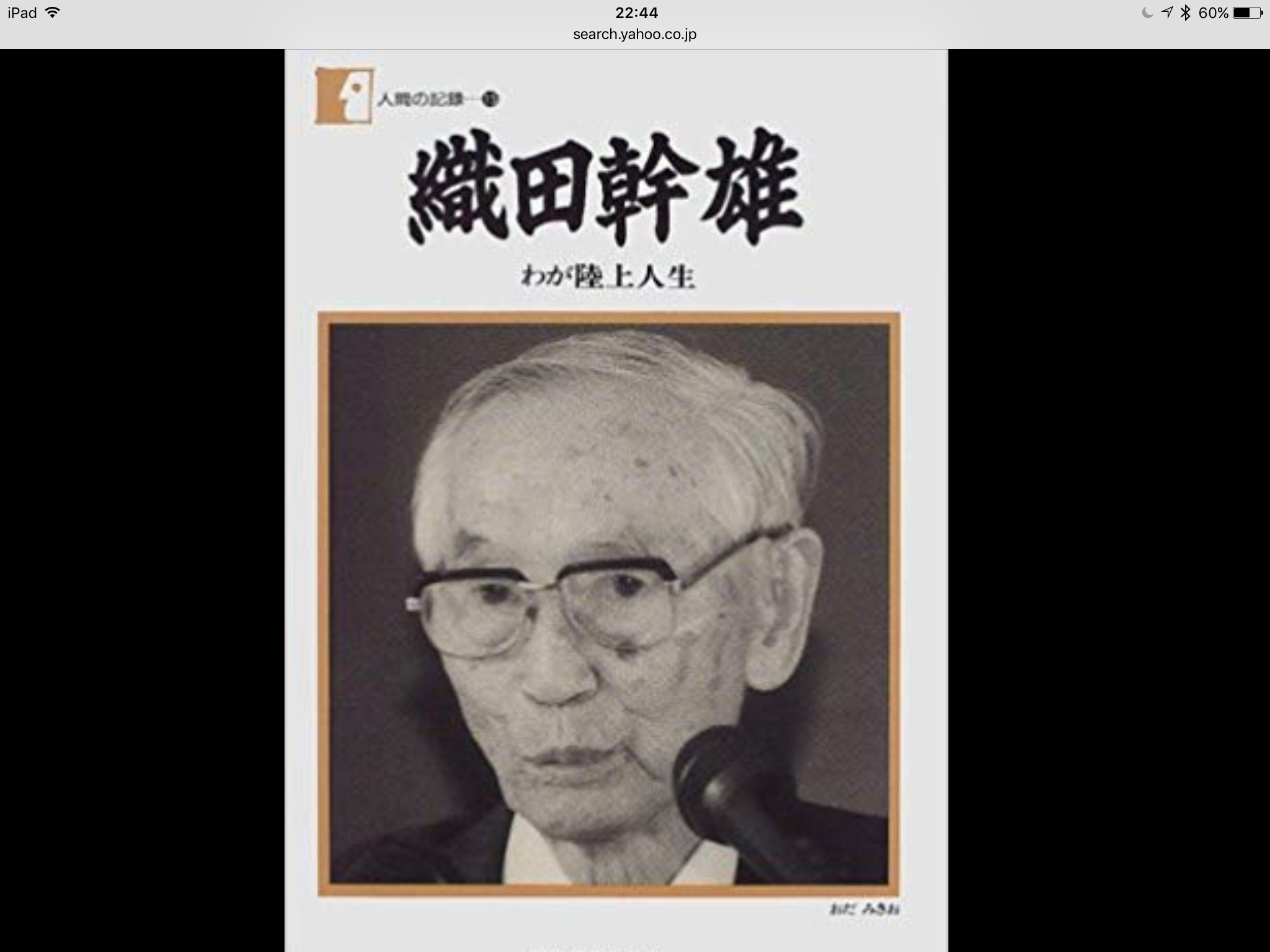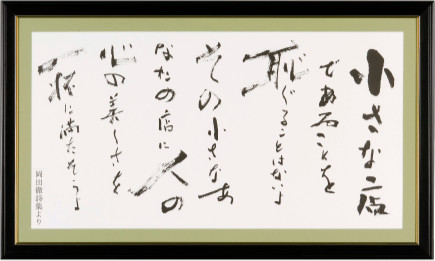Images of 手使海ユトロ

翌朝、出発前にボート乗船のグループ分けが書かれたボードを確認、その前にわらわらと集まっている地元の男の子たち(全員スタッフ??)の中から、ダイブガイドと称する青年が現れたので、彼にほぼすがるように、「自分は初心者だから絶対目を離さないでくれ、よく面倒を見ておくれ。」と懇願しておいた。
マングローブの泥の海岸からつき出た桟橋からボートに乗船、いざダイビングに出発。
当時はインターネットの存在どころか、詳細情報がほとんど無かったがために、正直ポイントまでボートでどのくらいかかるのか、どこのどんなポイントにダイビングに行くのかもわかっていなかった。今思えば当然あれがブナケン島だったわけだ。
島に近づくにつれ、何色も異なった青色がグラデーションを重ねて輝いている海面がこの世に存在する色とは思えないほど美しく、何度も何度も目をこらして見ては、それらの色全てをなぞり、記憶に焼付けようとした。
ブナケン島初ダイビング1本目はとにかく緊張もあって余裕が無かったせいか、残念ながらほとんど記憶に残っていない。海外でのダイビングは初体験ということもあり、言葉もイマイチ通じない初めての土地で、会ったばかりの地元ダイブガイドや外国人ゲストに一人混ざって潜る、というのはそれはそれは勇気のいること。不安に押しつぶされそうになっていたに違いない。
1本目のダイブですっかり緊張が解けた、と言いたいところだが、2本目のダイビングでとんでもない感覚に襲われることになった。
ダイビング開始後、15分くらい経過していただろうか。突然強烈な喉の渇きを感じたので一生懸命つばを飲み込んで渇きを癒そうとした。でも飲み込めば飲み込むほど喉がからからに渇いていく(ような気がした)。焦りが出て呼吸が早まり、レギュレーターからの吸気音がよけいに大きく聞こえる。
どーしても地上の空気が吸いたくなって、どうにも止まらない。
全身が神経になったみたいに感覚は研ぎ澄まされているから、一瞬のうちにたくさんの事を考える。
「タンクからエアが来ているんだから、呼吸ができていない訳じゃない」と自分を説得してみたり、
「今すぐ緊急浮上ってやつをやってしまおうか?あー、海上に出ておもいっきり空気が吸いたい!どーしても吸いたい!」
「海面までもつかな?」 海面を見上げ、手首にしているダイビングコンピューターが水深25メートルを表示しているのを確認、隣のガイドくんを見る。
「彼に知らせようか。あー、でもどうせ言葉が通じないし、わかってもらえそうもない。」
「今私が急浮上したら、(目の前で一緒に潜っている)彼ら全員がダイビングを中止しないといけないだろうから、後で彼らに恨まれるだろうな。参ったなあ。でも我慢できるだろうか…?!」
「あー、もうどうでもいい!地上の空気が吸いたい!」
こんなことが数秒のあいだ、頭の中をまさにぐるぐると駆け巡っていたのである。
わずかに残った理性と”悪魔のささやき”との正面対決であった。
すぐ手の届くところにガイドくんがいたにも関わらず、まだ他人のような彼を信用していなかったのか、恨めしく彼のほうを見つつも助けを求めようともせず、右手に広がる、どこまでも延々と吸い込まれそうな透明度のある紺碧の深みに目をやると、ますますどうにもならない。
ダイビングではやっては非常に危険な、”一気に浮上”したい衝動に襲われ、めまいさえするような気分だった。
「深みを見てはダメだ!」かすかに残る正気が私に呼びかける。
ふと気づくと、私のすぐ左手に垂直に続く珊瑚礁のドロップオフの壁が目に入った。
「そうだ!この壁に集中しよう。壁だけに神経を集中していればなんとかなるかもしれない。もう青いほうは一切見てはダメだ!」
「こうなったら、エアがさっさと終わろうが、全部かまわず吸い尽くしてしまえばいい。」
とっさにそんな決断をして、タンクの内壁まで吸い尽くすような大深呼吸を始めながら、珊瑚礁の壁に近づく。そこに群れる魚たちがようやく目に入る。
壁に生える美しくカラフルなソフトコーラルやホヤなどにじっくり神経を集中させると、喉の渇きがだんだん薄らいでいく。「大丈夫だ…これでなんとかなる!」
遠のきそうになっていた正常な意識がようやく体に戻ってきたような感じだった。いったん体と意識が一体化すると、あとは嘘のように喉の渇きも、鼓動もおさまって、呼吸が正常なリズムを取り戻すまでに大した時間はかからなかった。
あとで、この時起きた事件をガイドくんに話したら、当然ながら「なぜ僕にすぐ教えなかったの?!」と怒られた。そして一気に彼との緊張も解け、あとは話の洪水であった。
透明度の良すぎる海での、初心者ゆえの緊張からのパニックなのか、ダイビングでいわれている”窒素酔い”だったのかはなんともいえないが、これが初めての体験であり、その後同じ感覚に襲われたことは現在に至るまで無い。


![【中古】 BGM CD DHC SOUND COLLECTION/東方見聞録 手使海ユトロ / 手使海ユトロ / DHC [CD]【宅配便出荷】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo-omatome/cabinet/10210940/cdb2fewuk6iq3jwq.jpg?_ex=300x300)


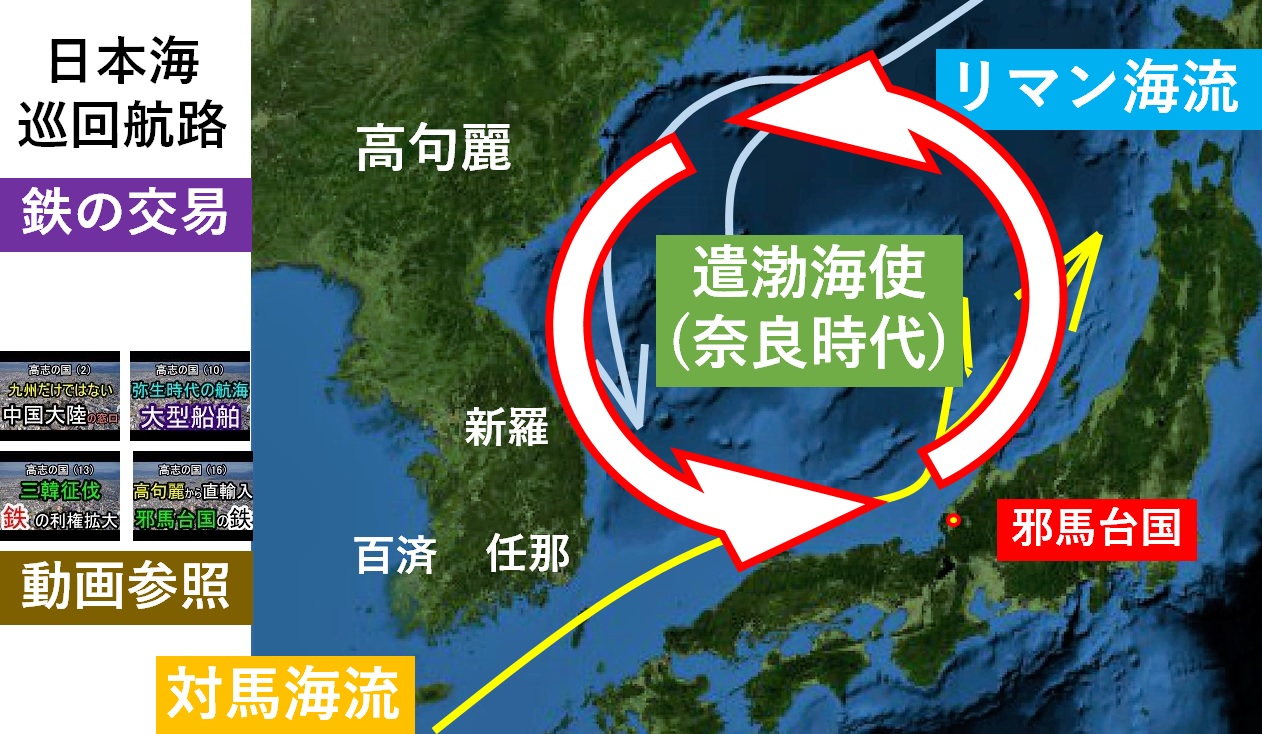
![手使海ユトロ(音楽) / Sound Track CD ねこぢる草 [CD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru2/cabinet/920/sadi-20.jpg?_ex=300x300)



![【中古】 ザ・モスト・リラクシング フィール(5)/(オムニバス),サラ・ブライトマン,中西康晴,伊藤佳奈子,手使海ユトロ,チェン・ミン[陳敏],千住真理子,マキシム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bookoffonline/cabinet/2478/0001425650l.jpg?_ex=300x300)
![遣渤海使一覧[百科マルチメディア]](https://japanknowledge.com/image/intro/kenbokkaishi3.jpg)
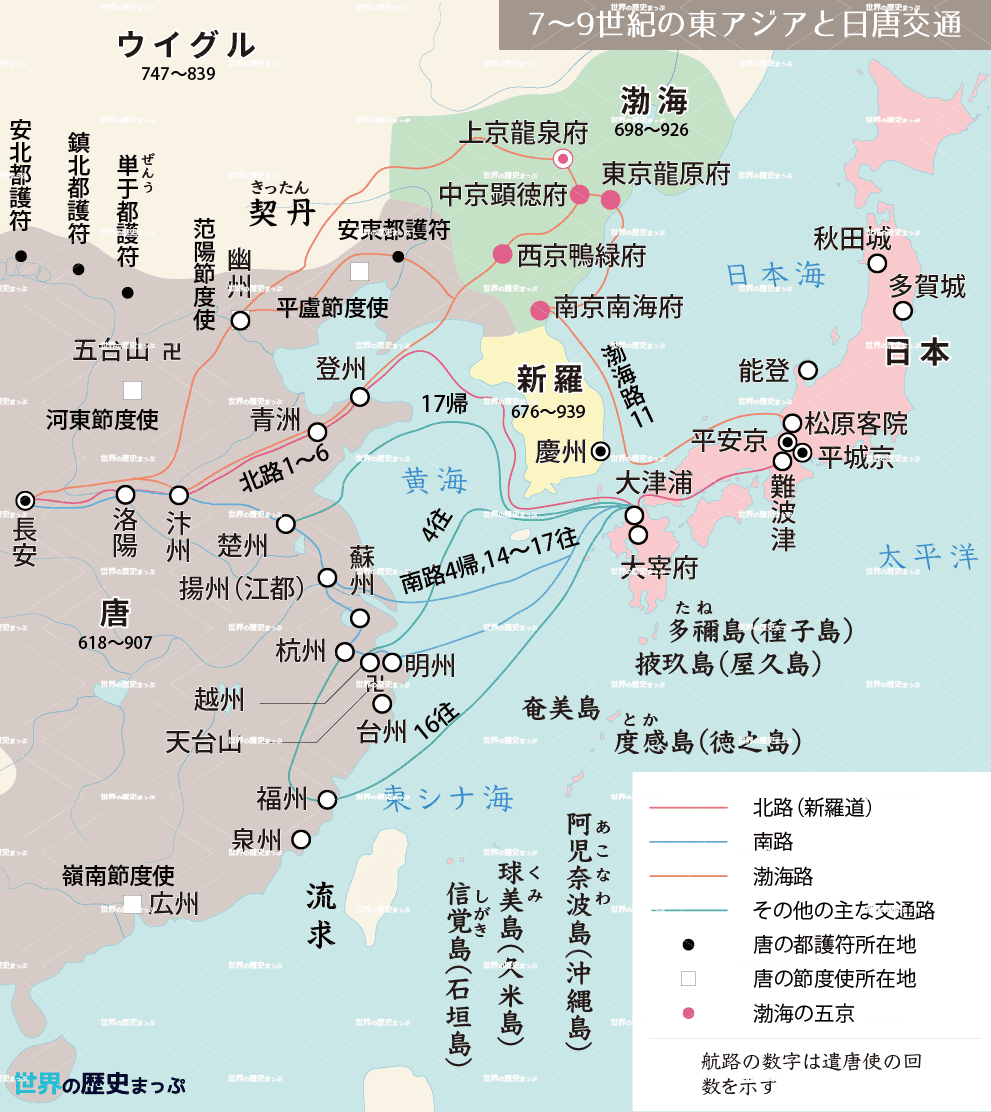
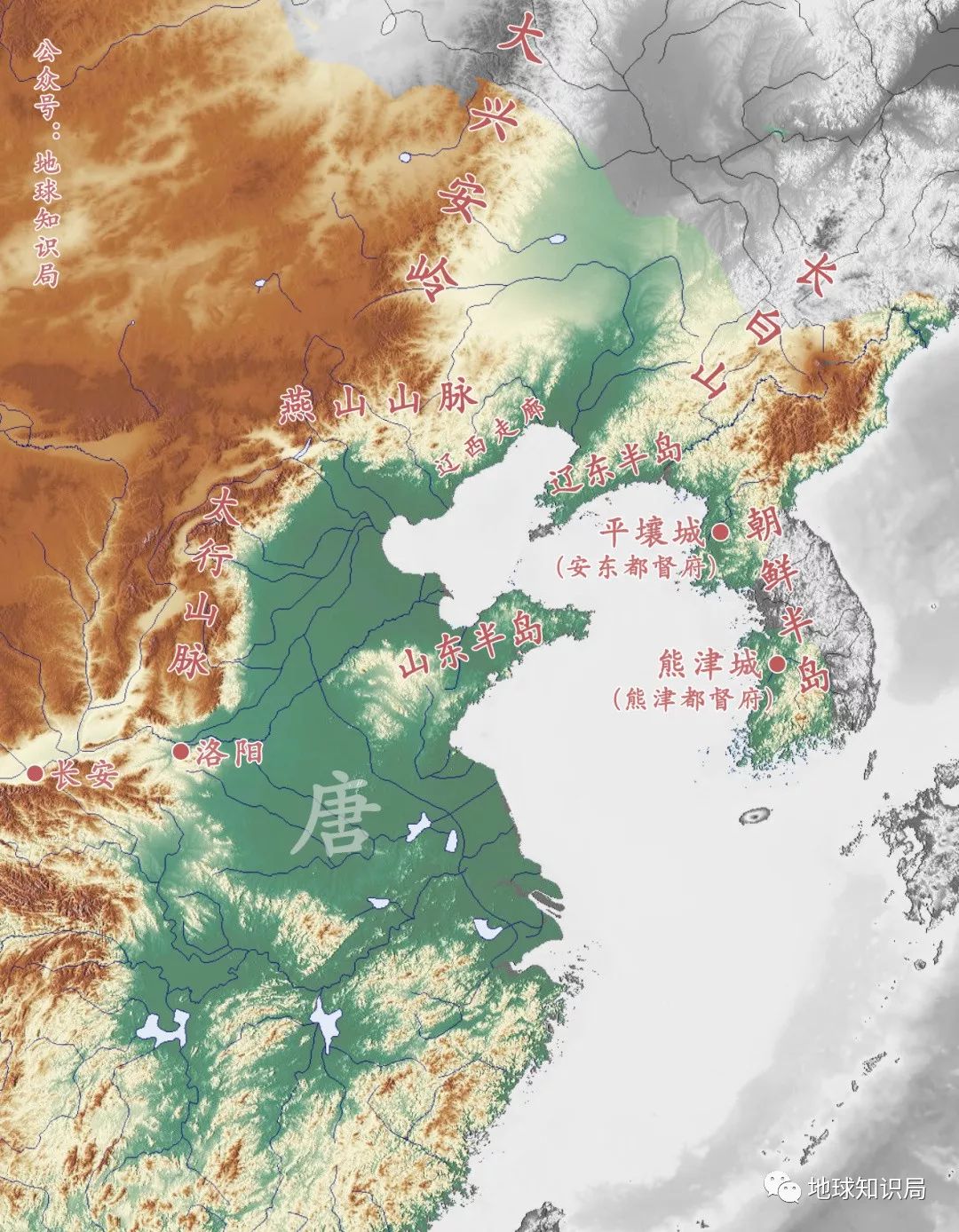
![【中古】 BGM CD DHC SOUND COLLECTION/東方見聞録 手使海ユトロ / 手使海ユトロ / DHC [CD]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/10211055/cdb2fewuk6iq3jwq.jpg?_ex=300x300)




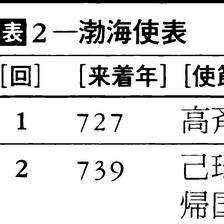
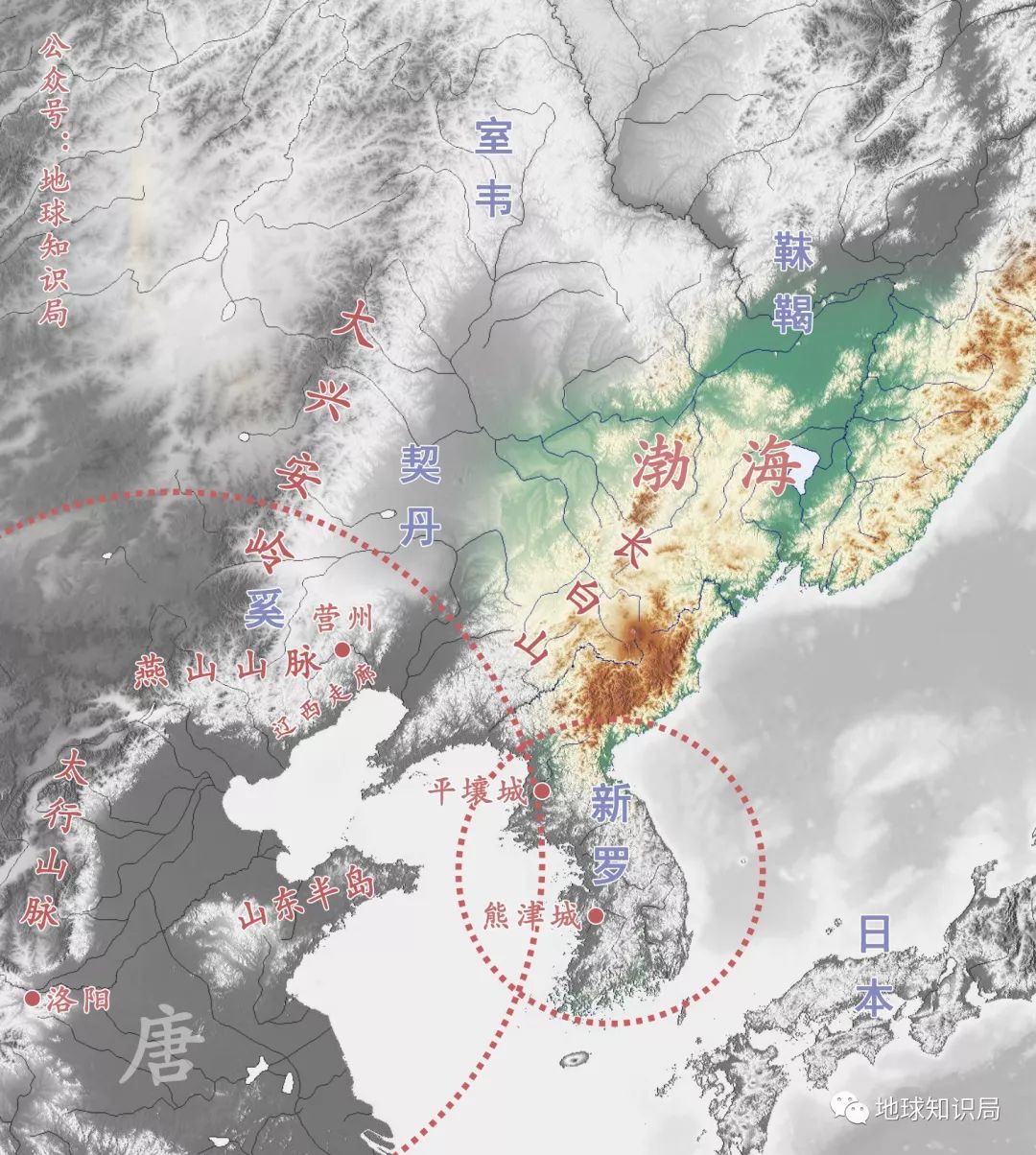

![Sound Track CD ねこぢる草 [ 手使海ユトロ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9920/4988044099920.jpg?_ex=300x300)
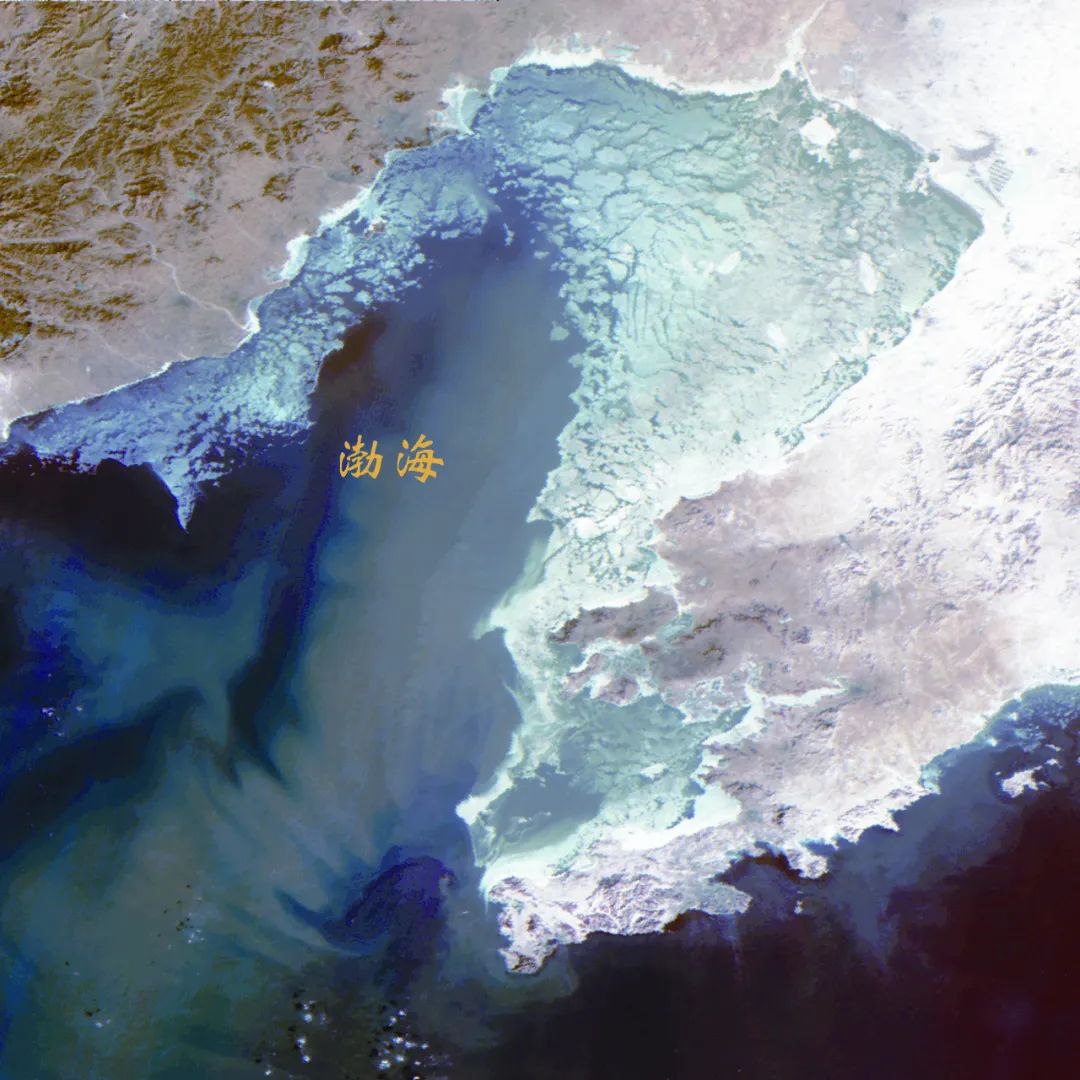




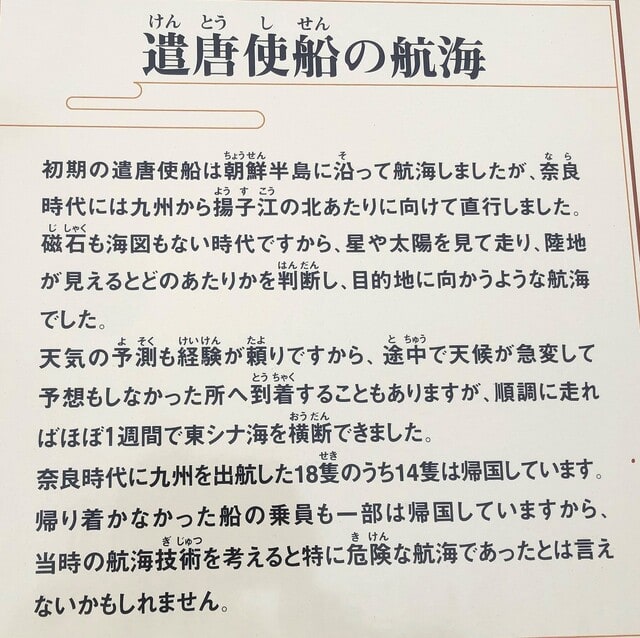


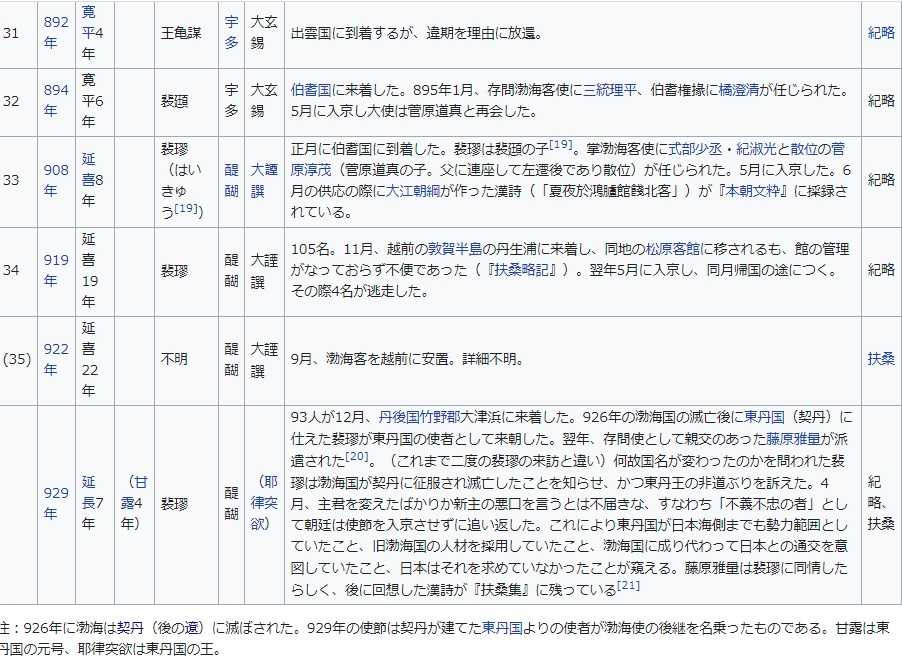


![【中古】銀河の魚〜URSA minor BLUE〜 [DVD] 監督・原作・脚本: たむらしげる 音楽: 手使海ユトロ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/2doriem/cabinet/sm29/sn29_b00005huyz.jpg?_ex=300x300)


![【中古】【非常に良い】銀河の魚~URSA minor BLUE~ [DVD] 監督・原作・脚本: たむらしげる 音楽: 手使海ユトロ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/skymarketplus/cabinet/sn29/sn29_b00005huyz.jpg?_ex=300x300)

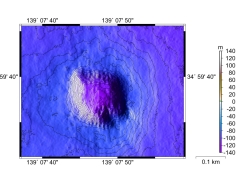






![黎明の堕天使ルシフェル Secret [ROTD-JP040]](https://takarajima0web.ocnk.net/data/takarajima0web/product/rotd/rotd040s.jpg)